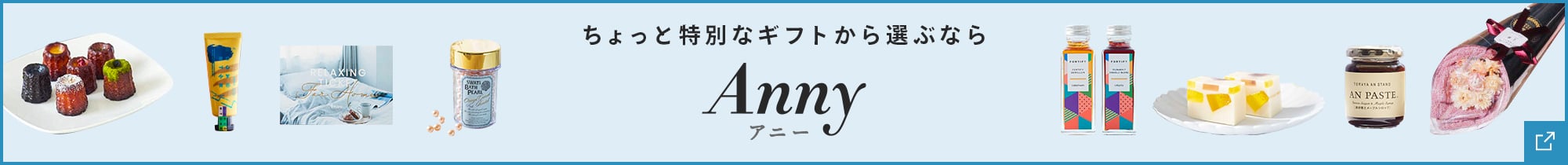- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
茶道具『朱漆竹花入 在銘「竹雲斎造」共箱+竹雲斎筆「竹の図」額』田邊竹雲斎 検:人間国宝 生野祥雲斎 竹工芸師 生野徳三 花入 竹花入れ
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
商品説明 サイズは、竹花入れ:径6×高さ29㎝です。 額:47,4×35,3㎝です。 多少の使用感はございますが、ダメージとなるような傷みはございません。美品です。一連のお茶道具はお茶の先生宅よりお譲りいただいたものです。 二代 田辺 竹雲斎 (明治43年(1910年) - 平成12年(2000年)) 本名:利雄。1910年、初代竹雲斎の長男として堺市に生まれる。5歳のとき、初代竹雲斎の個展会場で亀甲編みを披露。周囲を驚かせたというエピソードを持つ。9歳より、文人の教養として漢学者の土田江南に書を学んだほか、南画の素養も持つ。21歳のとき、編み込みの中に龍が踊る唐物風の「蟠龍図盆」で帝国美術院展覧会に初入選。以降、帝展、文展、日展に連年入選を果たしている。27歳のとき初代竹雲斎が他界し、二代竹雲斎を襲名する。この頃から作風が変わり、細く薄く削がれた竹籤による透かし編みを得意とするようになった。初代の得意とした重厚な「唐物」に対し、二代竹雲斎の作る籠は繊細で細やか、日本らしいとして「和物」と呼ばれた。 戦時中は河内長野に10年ほど疎開していたが、竹工芸を続けいきたいという信念から、終戦後まもなく高島屋で個展を行い、堺に戻った。勲四等瑞宝章、紺綬褒章を受勲し、日展評議員も務めている。60歳を過ぎてから「竹の特性に着いてゆけばええだけなんです」という心境に達したと語り、竹の癖や性質を生かすことを大切にしていた 三代 田辺 竹雲斎 (昭和15年(1940年) - 平成26年(2014年)) 本名:久雄。二代竹雲斎の長男として堺市に生まれる。大阪市立工芸高校 、武蔵野美術大学工芸工業デザイン科を卒業した。卒業後は堺に戻り、二代竹雲斎の下で本格的に竹工芸の道に進んだ。幼少の頃、疎開していた河内長野で遊んでいた矢竹を使い構成された作品が特徴である。硬く真っすぐに育つ矢竹の直線美を生かしたモダンな作品であった。 昭和になり、花籠やお茶道具という工芸品から、用途の無い芸術品がつくられるようになってきていた。三代竹雲斎は代々の伝統工芸品を制作しながら、オリジナルな竹のオブジェを制作も行うようになった。
残り 1 点 7000.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 05月23日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-















![KM#17/ドイツ 1/2マルク銀貨(1906)2.777 g,20 mm[E5164]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0511/users/3aedc1374b2bafb4006b44ad9303fd29ff17c6a1/i-img1200x1200-1732304227cgdz2q3234.jpg)